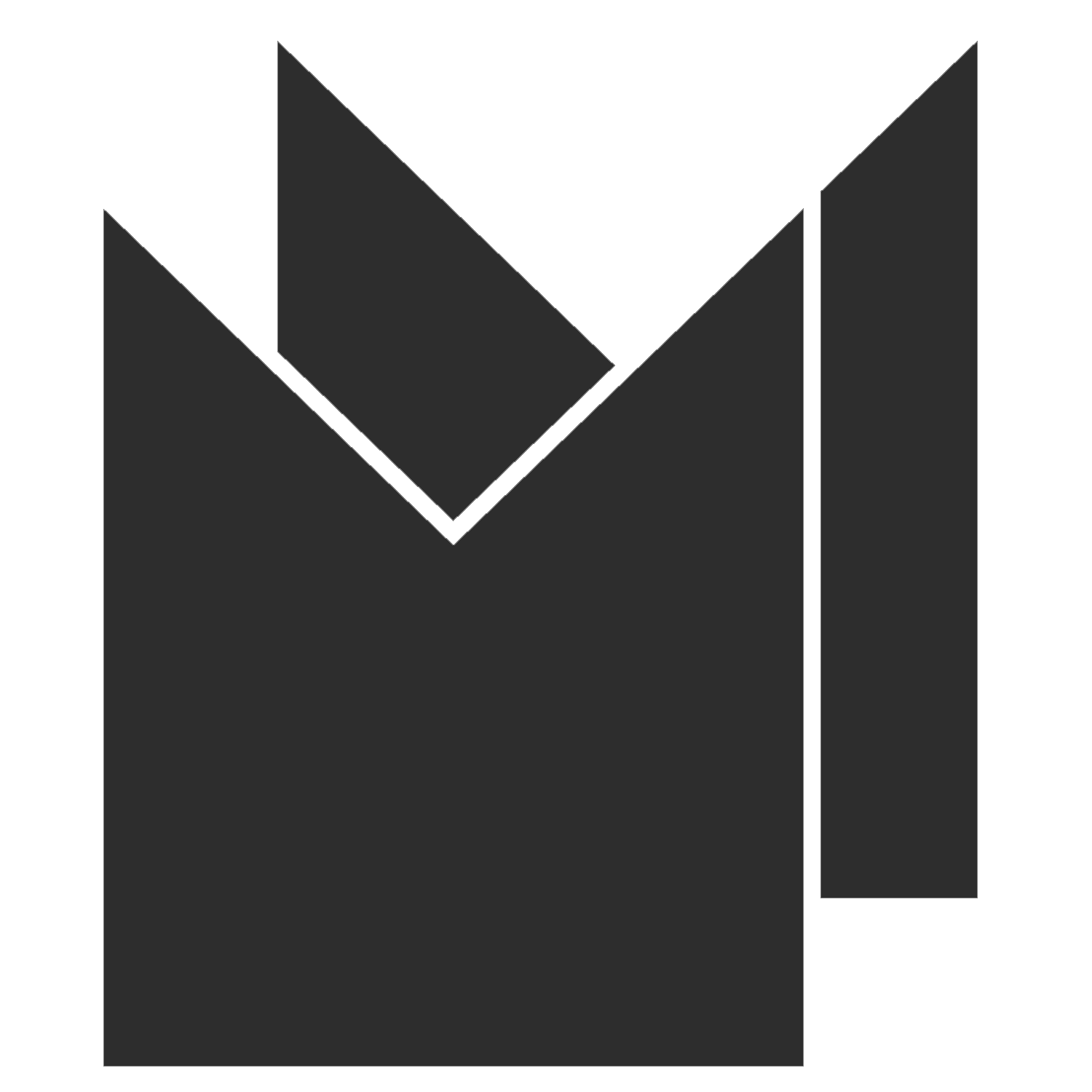生成AI(ChatGPT、Copilot、Geminiなど)を活用したアイデア企画発想法 6つのコツ |研修導入のご案内
20 / 05 / 15株式会社ウサギ代表の高橋晋平と申します。
おもちゃクリエーター|ビジネス創出ファシリテーターです。詳しくは以下のポートフォリオを見てみてください。

弊社、株式会社ウサギは全国の企業様を対象に「生成AIを活用したビジネスアイデア・企画創出研修」を導入しています。
生成AIを業務にまだうまく使えていない企業様に、まず基礎的な業務効率化活用法や企業内での活用リスクの話をお教えし、本題として、収益を生むアイデアを生成AIとともに作る方法を習得して頂いています。
生成AIは新しいアイデアを生み出すことが特に苦手と言われています。
それは、出てくるアイデアに新規性がないという意味よりも、生成AIが提案したアイデアを「実行し、価値を生み、利益を上げる」ことが難しいという点に本質があります。
アイデアは、実行者の能力や経験、内発的動機、言うなら「人生」と深く紐づいているから企画に成るわけで。
生成AIとの対話の中でアイデアをほめられ、もっともらしく推奨され、何だか良いアイデアに見えてきて嬉しくなって、
・実行することも忘れて満足したり
・プレゼンをして格好がついてなんか成し遂げた気になったり
・いざやってみようとしたら誰も協力者を巻き込めなかったり
ということに陥ります。
ここを乗り越えて、生成AIと一緒に、「実行し、価値を生み、利益を上げる」方法をワークショップ形式で学んでいただくのがこの研修
「生成AIを活用したビジネスアイデア・企画創出研修」
です。
その大枠の流れを、大切なポイントと共に、以下に紹介します。実際は受講企業様にプロンプト集を配布しつつ、会議室でのグループ形式や、チャット・共有ツールなどを使ったオンラインワークで進めていくものになりますが、以下の流れを参考にしていただくだけでも充分に有用かと思います。実際に僕が通常業務で多用している方法になります。
【前提】
・アイデア発散フェーズと、企画収束フェーズに分かれます。
・必ず紙への手書きを使います。
【流れと重要なポイント】
■アイデア発散フェーズ
① 自社(実行者)の強み・弱みを洗い出す
・誰が実行するか(どこの誰になって、自分事として考えるか)を定めます。
– その実行者(法人、企業内の個人など)の情報をリサーチさせ、学習させます。
– その実行者の強み、弱みを分析します。
② ニーズ調査とインサイト発掘
・ビジネス(商品やサービス)のアイデアを考える上で、そのビジネスが叶える顧客の「欲求」を定めます。
– ターゲット(例えば法人、こんな属性を持つ個人)などを決める
– お金を出しても解決したいニーズを推論し挙げる
– そのニーズの奥にある「インサイト(消費者も気づいていない深層心理)」を推論し挙げる
– 解決したら利益額が大きいと推計される順にニーズに優先度をつける。
– 実行者の強みを活かして解決できる確率が高いニーズに優先度をつける。
– ここまで検討した材料を(あくまで)参考にして、インサイトも鑑みながら、自分が据え置きたい欲求(企画するビジネスで解決したい欲求)を一旦決める。
③ 解決したい欲求に対するビジネスアイデアを、グラデーションをつけて出す
・無難でごくフツーなアイデアから、一歩ずつ、以下のようにアイデアの特徴を色濃くしていく
– 事業規模を大きくしていく
– 発想を飛躍させていく
– 既存事業に近いところから「飛び地」へ持っていく
– ペイン型事業に、ゲイン型事業の要素を付加していく
– 理解不能にしていく
など
■企画収束フェーズ(実行し、価値を生み、利益を上げる)
④ アイデアの選定と、企画案(実行するための計画)へ具体化する
・アイデアを、7つの基準で選定し優先度をつける。
– 優位性(実行者の強みを活かせるか)
– 具体性(最終形までイメージを描けるか)
– 実現性(あらゆる意味で、やれるか)
– 必需性(あらゆる競合よりこちらを選ぶ顧客が存在するか)
– 伝播性(全ステークホルダーに魅力が明瞭に伝わる速度がはやいか)
– 収益性(顧客が受け取る価値と、実行者が得る対価が充分か)
– 持続性(一歩目の実験を開始するハードルが低く、続けたいゴールにたどり着くまで破綻しないか)
⑤ 生成AIから離れて、紙に書く
・(あくまで)参考にビジネスモデルの各種キャンバスフォーマットに落とし込んでみる
・生成AIを閉じて、紙に書き、自分や他者と対話する。ここがこのプロセスの最重要ポイント。理由はこの記事の終盤に書く。
⑥ 生成AIにて、企画案の弱点探し、ステップバイステップ・対話形式によるアクションプラン作成
・紙に書いて整理した思考を、再度生成AIと対話しながら整理し、「実行し、価値を生み、利益を上げる」ためにどこがネックなのか、どう補完するかを探る。
・生成AIに質問してもらいながら、整えていく
・何度でも ⑤(紙、人との対話)に戻る
ざっと簡単に言うと上のような流れです。
研修では、この流れを体験して頂きながら、ビジネス企画を1つまとめ上げていただきます。
プロンプト集を提供しますが、結局はプロンプトも自身でカスタマイズし続けることが重要で、そのコツもお伝えします。
最後に、なぜ「紙」を使うのかをご説明しておきます。
皆さんは、有名で自信家で圧が強い起業家にビジネスアイデアを相談し、いろいろと意見を言われたら、その意見をどう処理すると思いますか?
その意見が優秀に思えてしまい、他の発想ができなくなり、でも言われた意見は自分では実行できないレベルの話で、結局何も動けない、ということになりかねない気がしませんか?
実は生成AIは、この例以上に厄介です。
生成AIは、やたらと褒めたり肯定したりしてくるものです。通常、人が期待する確率が高い「確からしい」答えを推論し出力をするので、生成AIが出した回答を「いいな」と思ってしまうのが必然なのです。そういうふうにできています。仮に「厳しい意見を言って」と言えば、今度はその厳しい意見が確からしく見えてしまい、自信がなくなる。その厳しい意見を何とかするアイデアを求めると、出てきたアイデアがさらに確からしく見えてしまう……。
そもそもアイデアとは、自分という個人に紐づいた「観念」であるから、それをもとに行動ができるわけで、何を最優先するかで言うと、そこから整えた企画が、「実行の一歩目を踏み出せるもの」になっていることがまず必須なのです。
そしてその次は、それが自分がうまく扱いクオリティを上げられる企画であることが必要。
ここに至るには、生成AIの画面を閉じる必要があるというのが、業務で活用している僕の現時点での「絶対」です。
生成AIは、超優秀な「ヒントツール」であり、ヒントツール以上にはなれません。知識やヒントを得ることで行動のきっかけや後押しはもらえるけど、事業構築をやるのは人によるチームでなければならないというポイントを外すわけにはいきません。きれいなそれっぽい資料が完成する所までしか行けません。
この話をすると「それは生成AIの使い方がわかってない」と返されることもありますが、そう言える人はそもそも自力でビジネスを作れる人であり、個々の能力や経験、内発的動機にフィットさせなければビジネスなんて立ち上げられません。しんどすぎます。
ということで、会社の事業領域と事業規模に合わせた新規事業企画立案から、私の小さな商売作りにまで使える本研修にて、ぜひ皆様の会社とご一緒できたら嬉しいです。
お問い合わせは以下より。回数、期間、人数規模、オフラインオンラインなど、様々な実施方法がありますので、Zoomでお打ち合わせさせてください。↓
しゃべり(TEDトークと、放送約1500回全アーカイブありのVoicy)↓